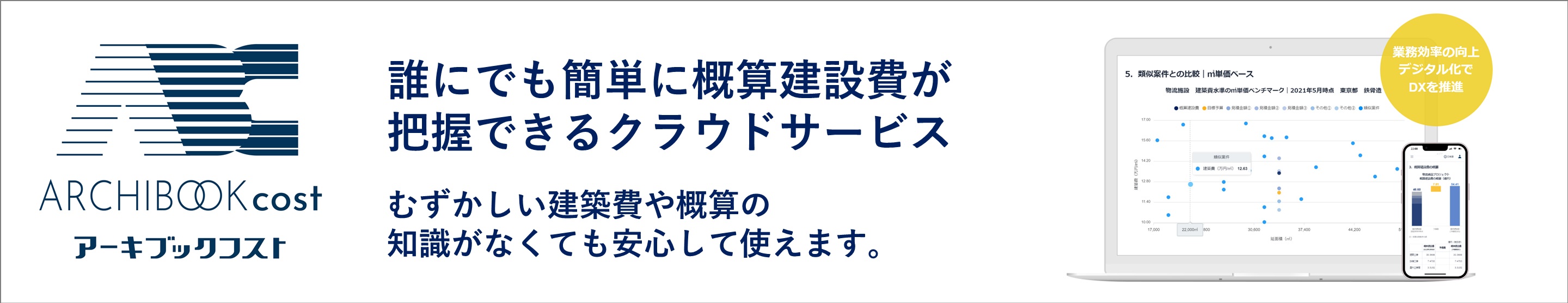地方活性化と建設業(3)〜経営の多角化がカギを握る〜
地方活性化と建設業の関わりについて考えるシリーズ、第2回では、地方における建設業界の生き残り策として、人材移動の利点と問題点を考察しました。第3回は、地方から人材を流出させない人材移動策として注目されている経営の多角化について、事例をもとにメリットや課題を考察していきます。
地方建設業の経営多角化の目的
地方における建設需要は、市場規模が小さいために繁閑の波が大きいことが問題です。閑散期に合わせて建設業者が淘汰され人材が異業種に流出してしまうと、地方活性化の流れが起こった際の建設需要増加に対応できなくなったり、建設技術が低下してしまう恐れなどがあります。
そこで、建設需要が低下している時期でも、人材を外部に流出させずに、異業種で仕事を確保することが建設業の経営多角化の目的です。
多角化成功のカギは建設業の技能や機材を生かすこと
業績悪化に悩む企業が経営の多角化に活路を求めることは少なくありませんが、当然ながらノウハウを持っていない異業種参入のハードルは高く、失敗するリスクは低くありません。
経営の多角化を成功に導くためには、建設業者が持っている技能や機材、資材などを生かせる事業であることが必要になります。具体的には土木用の重機の活用や、解体した廃材の再利用、職人の持つ手先の器用さなどを活用することなどが考えられます。
異業種参入の柱となる農業への進出
現在、多角化の事例としてもっとも目立つものは農業分野への進出です。大きなメリットとしては、畑の整備に建設業者の保有する重機が役立つことが挙げられるでしょう。
例えば、遊休土地や耕作放棄地を畑として整備するには、地面を大規模に掘り起こして土壌改良を行う必要があります。しかし、通常は費用がかさみ、農業を始めても採算が得られるには長期間を要するため、畑としての再活用が実現することは非常に少なかったのです。
しかし、建設業者であれば、閑散期に自社の重機と人材を投入して低コストで畑の整備を行えるため、早期に採算ベースに乗せられる可能性が高くなります。また、建設労働者は普段から屋外作業に慣れており、体力も総じて高いため、農作業への適性もあります。収穫した作物の運送でも、保有するトラックや重機の活用が見込めます。さらに、余剰資材や、建築廃材などを再利用してビニールハウスを低予算で作り、農業に活用している事例なども見られます。
農業参入における注意点
遊休土地などの再利用では、建設業者の能力を生かせますが、作物を育てるノウハウは一朝一夕には習得できません。素人が知識を持たずに農業に取り込んでも、市場価値のある農産物を作ることは難しいでしょう。専門家の指導を仰ぎ、時間をかけて十分に準備をする必要があります。
農業に参入する場合、既存農家への配慮も重要です。地元農家の経営を圧迫するようなことがあれば、農業組合などの協力が得られなくなり、農業参入の成功率は低くなるでしょう。仮に成功したとしても、地元農家にダメージがあれば、地方経済に悪影響を及ぼし、地方活性化により地方建設業界を再生するという本来の目的から外れてしまいます。その為、市町村や農業組合とよく相談したうえで、どのような作物をどれだけ作るのか計画を立てたうえで参入することが重要となります。
「地方活性化と建設業」はこちら↓
(1)建設業の果たしてきた役割と現状
(2)人材移動の功罪
(3)経営の多角化がカギを握る
(4)経営多角化の事例
「関連記事①-災害と建設業」はこちら↓
(1)災害発生直後の対応
(2)災害復興最初期の対応
(3)災害復興初期の対応
(4)災害復興中期の対応
(5)災害復興後期の対応
(6)災害復興対応のまとめ
「関連記事②-建設業の社会保険未加入問題」はこちら↓
(1)現在の状況と問題の背景
(2)ガイドライン改訂の影響と今後の予測