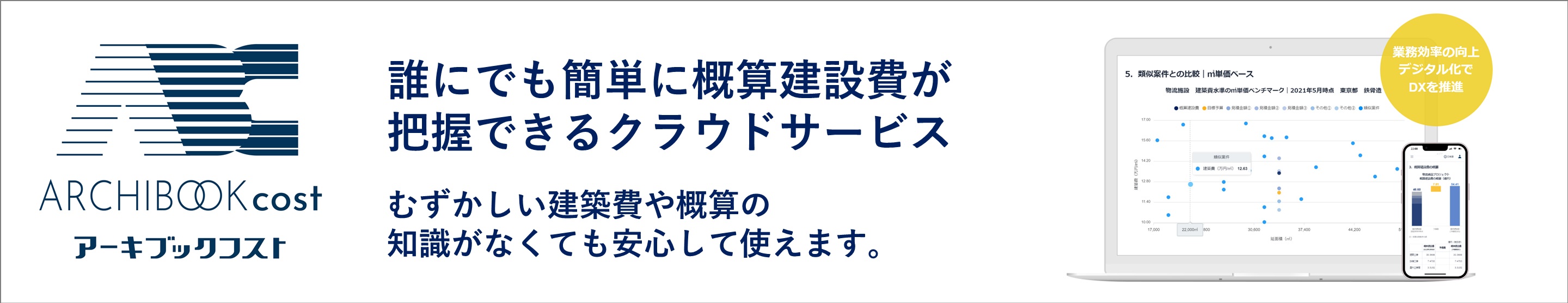地方活性化と建設業(1)〜建設業の果たしてきた役割と現状〜
昨今、国内の大都市では建設市場が活況で、ゼネコンなどの大手を中心に増収・増益が伝えられています。その理由として、東日本大震災の復興特需や2020年東京オリンピック特需の影響もありますが、それ以上に、社会構造が大都市一極集中の方向にシフトしていることが挙げられるでしょう。
その反動もあって、地方都市などでは、経済が停滞し、建設業界だけでなく、地域全体が苦境に陥っています。地方の活性化や地域再生は、今後の日本を支えるために必要される課題ですが、建設業は地方活性化の課題にどう取り組んでいけばいいのかを考えてみます。
第1回は、地方都市において、建設業がこれまで果たしてきた役割と、現在の状況を考察します。
高度経済成長とともに成長した建設業界
高度経済成長期、国の発展を支えたのは、ライフラインや交通網、商業ビル、住宅などの社会基盤の整備事業でした。
社会基盤が整備されることで、地域の生活環境が向上し、企業や人が集まります。同時に、建設に投資された資金は、建設業者を通して地域に循環され景気も向上。さらに、それによって増加した人口の雇用の受け皿としても建設業は重要な役割を担っていました。つまり、高度経済成長とともに建設業界は成長してきたのです。
公共事業と建設業の結びつきと聞くと、現代だと、癒着や談合いったダーティーななイメージがつきまといますが、本来は国の発展に必要なことであり、悪いことではありません。むしろ経済成長を遂げた国家では必ず発生する現象であるといえるでしょう。
高度経済成長の終焉をハードランディングした日本
社会基盤の整備が一巡すると、高度経済成長は終焉に向かいます。このとき建設業界は、適度に規模を縮小し、社会基盤の維持を担っていく安定産業にシフトチェンジすることが理想的なシナリオでした。
しかし、高度経済成長の終焉期の日本は、世界情勢などの影響もあって内需拡大の必要に迫られ、必要な社会基盤の整備が終わりつつあるのにも関わらず、公共投資を増大させていきます。その結果バブル景気に突入し、建設業界は肥大化を続けました。
そして、バブル経済の崩壊というハードランディングで高度経済成長期の終焉を迎えたことで、肥大化した建設業界は安定産業へのシフトチェンジが行えず、不況の荒波に飲まれていくのです。
公共事業費の削減が始まり、地方の建設業界が苦境に
バブル景気の崩壊により、世の中は大不況に突入していきます。それによって地方では民間の建設需要が大幅に減少しますが、国や地方自治体は地方経済や雇用の維持のため、公共事業を増加させていきました。
公共事業を増大させる経済政策は一定の成果を上げて、地方の建設業界に致命的な打撃が加わることを防ぐことに一時的に成功しましたが、その間に地方建設業界の公共事業依存体質は一層進んでしまいます。
そして、21世紀に入り、社会的な批判の強まりを受けて、国は公共事業の削減政策に転換。これにより、公共事業への依存性が高まっていた地方の建設業界は深刻な不況にあえぐことになっていきました。
次回は、公共事業削減時代の地方建設業界の生き残り策について紹介します。
「地方活性化と建設業」はこちら↓
(1)建設業の果たしてきた役割と現状
(2)人材移動の功罪
(3)経営の多角化がカギを握る
(4)経営多角化の事例
「関連記事①-災害と建設業」はこちら↓
(1)災害発生直後の対応
(2)災害復興最初期の対応
(3)災害復興初期の対応
(4)災害復興中期の対応
(5)災害復興後期の対応
(6)災害復興対応のまとめ
「関連記事②-建設業の社会保険未加入問題」はこちら↓
(1)現在の状況と問題の背景
(2)ガイドライン改訂の影響と今後の予測