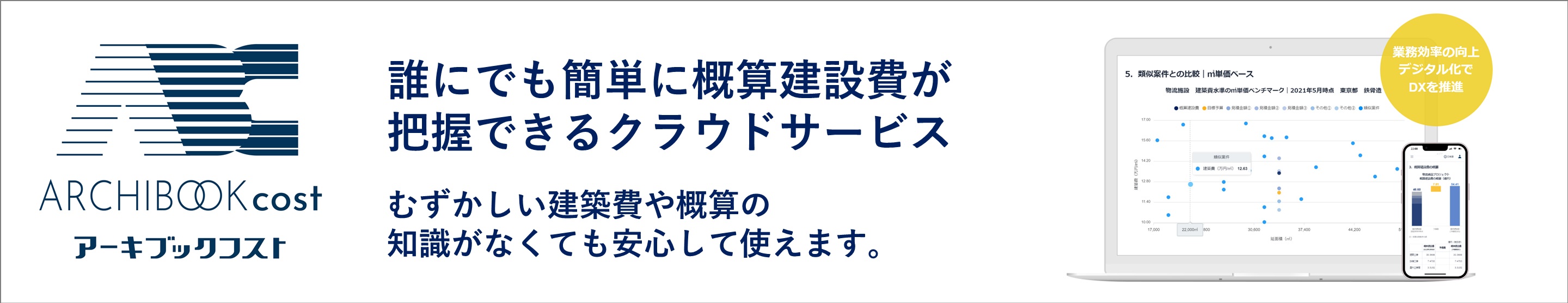エネルギーマネジメントシステムのHEMS、BEMSとは(2)〜HEMSによる家庭の省エネ〜
エネルギーマネジメントシステムについて考えるシリーズ、第2回は家庭用のシステムであるHEMSについて紹介します。
HEMS(Home Energy Management System)とは
HEMSのHはホーム、つまり家庭用のエネルギーマネジメントシステムのことを表します。第1回でエネルギーマネジメントシステムとは、効果的に省エネを実現するためのシステムであると紹介しましたが、具体的にはどのようにして省エネを実現するのでしょうか。
HEMSの中核をなす装置は、スマートメーターで計測した電力の使用量をデータで受け取り、集計して、利用者に見えるように表示するための一連の装置といえます。実際の利用イメージとしては、キッチンやリビングなどにモニターを設置し、電力の使用量をチェックして、省エネの実現度を確認するということになります。また、モニターではなく、家庭のテレビに表示したり、パソコンにデータを取り込んで、表示するだけでなくデータを二次的に利用することも可能です。
もちろん、電力の使用量が把握できるようになったからといって、即時に省エネになるわけではありません。続いて、HEMSが示すデータを省エネにつなげるための方法を調べていきましょう。
省エネへの意識を高めることができる
これまで、電気の使用量については、電力会社からの毎月の請求内容で確認するしか方法がありませんでした。この方法だと、例えば省エネ効果の高い家電を購入しても、結果を確認できるのは早くても一か月後になってしまいます。また、電力の使用量は外出が多ければ少なくなりますし、夏場や冬場はエアコンの使用で多くなるなど、日によって、季節によってばらつきがあるため、なおさら省エネ効果を実感することが難しくなります。
HEMSを利用すれば、省エネ家電を導入したその日から、電力の使用量がどう変化したかを確認することができます。省エネ効果を実感できれば、省エネ家電を導入する意欲も高まることでしょう。また、こまめに消灯する、冷蔵庫の開け閉めを減らす、冷房の温度設定を1℃上げるなどの省エネ行為の効果も具体的な数値で確認できるため、より意識が高まることが予想されます。
ピークカットやピークシフトが容易になる
1年のうちでもっとも電力需要が高まるのは、冷房が使用される夏場の日中です。電力会社はこの電力需要のピーク時に対応できるだけの発電能力を用意する必要がありますが、火力発電所は簡単に出力を落としたり、停止させることが難しいため、ピーク時以外には発電量が余剰することがあります。余剰した電力の一部は揚水発電などによって蓄えられますが、多くの余剰電力は捨てられているのが実情です。
この問題を改善する方法としてピークカットやピークシフトがあります。ピークカットは、電力需要が最も高まる時間帯に電力使用量を減らす努力をすること。ピークシフトは、例えば電力需要の低い夜間にバッテリーなどの充電を行い、日中のピーク時はバッテリー給電で家電などを稼働することで、ピーク時の電力使用量の一部をほかの時間帯に移すことなどをいいます。
将来的には、各家庭で容量の大きな蓄電池を活用することが目指されており、HEMSは電力需要のピーク時に合わせて、自動的に蓄電池からの給電に切り替えるなどの対応を行うことができます。これにより、電力需要のピークがならされると余剰電力が減って、大幅な省エネにつなげることができます。
電力自由化とHEMS
2016年に始まった電力の自由化により、電力会社以外でも電気を販売することが可能になり、電力の販売方法も多用化しています。例えば、夜間の電気代が安くなるプランや、オール電化など、電気使用量が特に多い家庭向けのプランなど、様々なライフスタイルに合わせたプランも登場しました。
しかし、実際にどのプランが自分の家に向いているのかを考えてみると、なかなか判断が難しく決めかねることも多いでしょう。こうした場合にHEMSが導入されていれば、各種プランを導入した場合の電気料金の試算を、実際の使用状況をもとに行えるため、どのプランが最もお得なのかが一目瞭然となります。
また、家電製品もHEMSによりコントロールすることに対応した製品が増加しており、近い将来HEMSは家庭の必需品となることが予想されます。
「エネルギーマネジメントシステムのHEMS、BEMSとは」はこちら↓
(1)一家に一台の時代がやってくる
(2)HEMSによる家庭の省エネ
(3)企業向けのBEMSとFEMS
(4)目標はスマートシティの実現
「関連記事①-環境に配慮した建設」はこちら↓
(1)建設がもたらした環境破壊
(2)見直される木材建築
(3)新時代の土木工事
(4)清浄な土壌を取り戻す取り組み
(5)超耐久建築は実現するか
(6)都会のオアシス 屋上緑化
「関連記事②-自然エネルギー活用建築とは」はこちら↓
(1)パッシブデザインの考え方
(2)環境配慮型の新技術
「関連記事③-建設業を変革しえるBIMとは?」はこちら↓
(1)BIMとは何か
(2)ソリューションとしてのBIM
(3)BIMの導入状況と課題