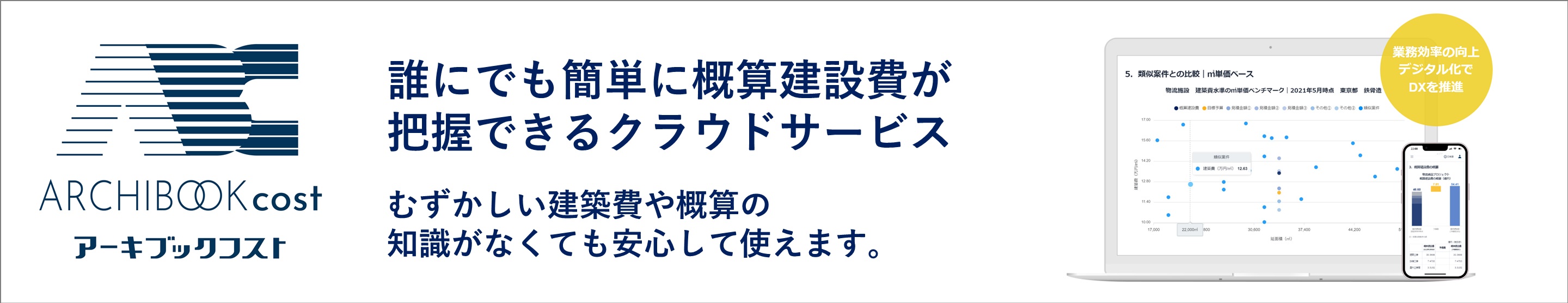建設業界の人手不足の現状と対策(2)~人手不足の根本的な要因~
建設業界の人手不足と対策を考えるシリーズ。第1回では、人手不足の現状と、きっかけとなった直接的な要因や現場の状況について調べました。今回は、より根本的な要因として、建設業界が長年就労先として不人気な理由を考えていきます。
復興特需が人手不足の真の理由ではない
2014年頃にピークを迎えた建設業界の人手不足は、少子化により全ての業界が人手不足になっているところに、東日本大震災による復興特需が発生したことにより一気に加速した背景があります。特需が一段落し、労働者の賃金も上がった現在は人手不足は解消しつつありますが、抜本的な問題は解決していないといわれています。
建設業への就労者数は、バブル期と団塊ジュニア世代の就労が重なった1995年頃をピークに減少に転じました。これはほぼ全ての業界で同じことがいえますが、国土交通省による調査によれば、20歳~24歳の全ての業種への就労者数のうち、建設業に就労する人の割合は、95年が6%以上に達していたのに対して、2010年には2.4%と大幅に下落しています。
このことは、建設業界が就労先として人気がないことを表しているといえるでしょう。
特需などの一時的な景気による人手不足の問題よりも深刻な問題で、抜本的な対策を行わないと、近い将来に致命的な人手不足に陥る恐れがあります。
3K職場のイメージが払拭されていない
「3K職場」という言葉が流行したことがあります。3つのKは「きつい」、「きたない」、「きけん」を表したもので、ほかの職場に比べて割りが悪く嫌われる職種であるということです。
3Kとされた職種の多くは体力系の仕事であることが多く、建設業界はその代表格とされてきました。また、建設業は「給料が安い」、「休暇が少ない」、「かっこ悪い」の3つも加わった6K職場であるといわれたこともあります。
こうした印象はあくまでも外面から見た印象でしかなく、必ずしも実態を正確に表しているものではありません。3K職場という言葉が流行したのは1990年代のバブル期で、当時はトレンディやスマートといったイメージが優先される時代であったために、特に建設業界が嫌われたという背景もあります。時代が変わった現在では、建設業をかっこ悪いと評する若者はあまり見られなくなっています。
ただ、全ての要素が払拭されたわけではなく、きつい、きけん、給料が安いといったイメージはいまだに残っているのも事実です。
度重なる不祥事や問題発覚で追加された悪いイメージ
3Kや6Kといったイメージのほかにも建設業界が忌避される理由があります。バブル期などに多発したゼネコンの汚職事件や、談合などの不祥事、あるいは、手抜き工事や施工不良などの問題に、悪い印象を持っている人は多いでしょう。
現代社会はお金に関するダーティーなイメージや、ずさんな企業体質には非常に敏感なため、こうしたイメージを払拭しない限り、人気の回復は困難です。
また、バブル崩壊やリーマンショックなどの経済危機の際に、多くの人材をリストラしたことにより、景気に左右されやすい不安定な職種であるという印象を与えました。
こうした職場は、就職を指導する教師や、親からも嫌われるため、ますます就労者が減る傾向にあります。
旧態依然とした業界構造も嫌われる要因
ゼネコンなどの大手以上に人材の確保に苦労しているのが、地元に密着する中小の建設業者です。建設業界は大きな受注はゼネコンが独占し、中小の建設業者はその下請けとして受注する構造になっています。その構造のせいで、賃金のレベルは会社の規模に比例しているのが普通です。
ほかの業界では、中小企業であっても高い技術力を持っていれば大きな収益をあげることが可能で、中には世界のトップシェアを誇っている中小企業も存在します。能力のある優秀な社員の賃金が大手企業の社員の賃金を上回ることも珍しくありません。
ところが、構造的に中小企業が下請けから脱却できない建設業界では、高い技術力を持っていても大きな収益をあげることができず、就労先として忌避される要因になっています。
◇実務で役立つ建築費の相場【最新版】TOPへ
◇実務で役立つゼネコンの状況把握【最新版】TOPへ
◇業績から把握するデベロッパーランキング【最新版】TOPへ

「建設業界の人手不足の現状と対策」はこちらから↓
(1)現在までの状況
(2)人手不足の根本的な要因
(3)就労先として人気を得るには
(4)新たな発想で人手不足を解消する
「関連記事-働き方改革が建設業に与える影響」はこちらから↓
(1)2018年現在の状況を整理
(2)工期や建設費への影響
(3)建設業で週休二日を実現する為に
「関連記事-建設業の社会保険未加入問題」はこちらから↓
(1)現在の状況と問題の背景
(2)ガイドライン改訂の影響と今後の予測
「関連記事-人手不足の深刻化が進む建設業における外国人技能実習生活用の実態」はこちらから↓
(1)外国人技能実習生ニーズの現状
(2)実習生の採用から受け入れ
(3)採用のメリットとデメリット