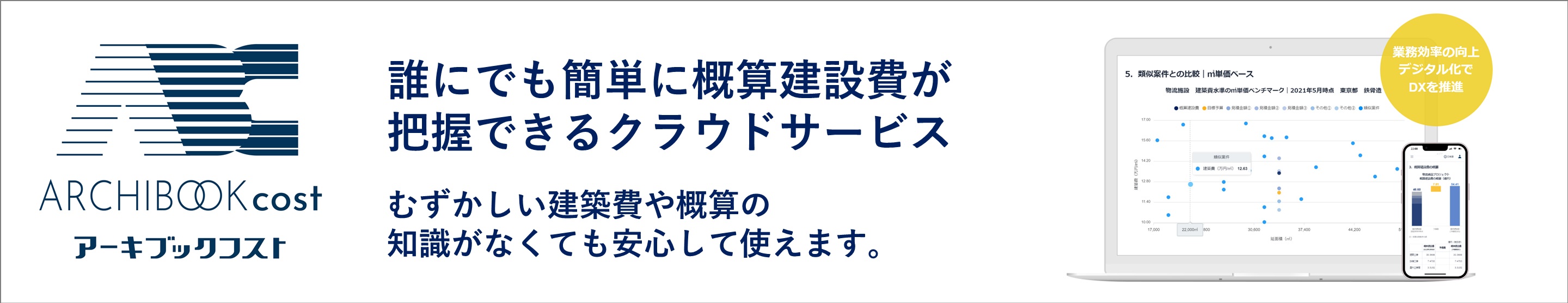建設業許可の基本①~概要と種類~
2020年の東京オリンピック開催が決定したこともあり、昨今首都圏を中心とした建設ラッシュが起こっています。国土交通省によると平成27年度に許可を新規取得した業者数は対前年度13%増とあり、申請数自体もかなり増えていることが推測されます。
そこで、本コラムでは今さら誰にも聞けない建設業許可に対する基本中の基本を改めてまとめていきます。許可の要件だけでなく、そもそも許可が必要なのか、取れるのか、どんな効果があるのか、までをお話ししていきます。
1. 建設業許可とは?
建設業許可とは建設業を営もうとする事業者が原則として取得しなければならない許可
であります。(建設業は建設工事の完成を請け負う業務であり、元請、下請、いかなる形態であるかは問われません。)現在こちらのページで示す29種類の業種に分類されており、該当する建設業を営もうとする場合、その業種の許可が必要になります。
※平成28年6月以降、元々の28業種に解体業が追加され29業種に変更されました。
2. 建設業許可の必要性を考える
前述の通り、建設業許可は建設業を営む事業者のすべてに原則として取得を促している制度です。その内、軽微な工事のみを行う事業者についてはその対象から除かれるとしています。つまりは、元々取得義務があり、一部の業者については免除が許されるものです。
具体的には、下記1)および2)に該当する場合は免除されます。
1)建築一式工事の場合(下記のどちらかに該当する場合)
・工事1件に対する請負金額が税込1500万円未満の場合
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものをいう)
2)建築一式工事以外の場合
・ 工事1件に対する請負金額が税込500万円未満の場合
「許可は取らなくてもいいと思っていた。」という認識のまま着工し、気付かぬうちに違法行為とならぬよう注意が必要です。また、工事を受ける側だけでなく、発注側の責任も問われることがあります。

3. 自分に必要な建設業許可の種類は?
建設業には幾つかの区分があります。
誰から、どんな許可をもらうのか、なんの業種で申請するのか?の判断を間違えると許可の取り直しとなりかねません。
1)業務規模
まず、請け負う業務の規模によって、許可の種類が異なります。
・特定許可
発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。
・一般許可
下請けに出す際の代金が上記を下回る場合、もしくは下請けのみを行う場合は一般許可を取得します。
2)業務範囲
また、建設業では業務の範囲によって大臣許可(全国)と知事別許可(都道府県)とに分かれ、許可を出す行政が異なります。
例えば、東京都に営業所があれば東京都知事(都道府県)による許可が必要になりますが、営業所が東京都と神奈川県にある場合には都知事の権限では許可が出せないため大臣(全国)による許可が必要になります。また、東京都に複数の営業所があっても、他県に営業所がなければ都知事の許可で問題ありません。
因みに、この許可は仕事(工事現場)の制限をするものではありません。あくまでも営業所、つまり契約を締結する場所についての許可をだしているだけですので、東京都知事の許可であっても、千葉や神奈川をはじめ全国で工事をすることが可能です。
3)業種
建設業の業務は幅広く、家を建てるところから、内装や造園、塗装などまで全てが建設業です。当然ですが、電気工事の専門業者は造園工事に強いわけではありませんし、その逆もしかりです。そのため、日本では建設業を29の業種に分け、それぞれの分野で許可を取得することを求めています。(平成28年6月に解体業が追加されました)
例えば、電気工事しかしていなかった業者に塗装の許可は取れませんし、電気工事の建設業許可を持っていたとしても塗装工事は行えません。
※詳しい業種についての名称とその内容についてはこちら
芹澤裕次郎のコラムシリーズ「建設業許可の基本」はこちらから↓
①概要と種類
②メリットデメリット・費用・審査期間